近年、心不全患者が増加傾向であり「心不全パンデミック」といった言葉を聞くようになりました。
私は急性期病院に勤務していますが、心不全患者は確かに増えたと感じています。
みなさまも心不全患者を担当する機会が増えると思いますので、ぜひここで勉強していきましょう。
この記事を読んでわかること
- 心不全の病態や治療
- 心不全患者に対するリハビリテーション
公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!
心不全パンデミック

日本は世界でもトップレベルの超高齢化社会であり、高齢心不全患者の大幅な増加が予測されており、このことを心不全パンデミックと呼びます。
心不全は再入院を繰り返す特徴があり、このまま高齢心不全患者が増加すると病院は飽和状態になってしまいます。
そのため、心不全を理解して発症・再発予防に努めることが重要です。
心不全とは
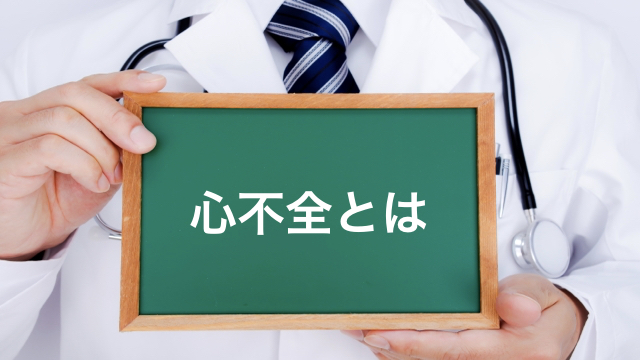
日本循環器学会が提唱する急性・慢性心不全診療ガイドラインでは、心不全を以下のように定義しています。
なんらかの心臓機能障害、すなわち、心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群
引用:日本循環器学会 急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)
心不全患者の多くは左室機能障害が関与していることが多く、左室収縮能による分類が多用されています。
左室収縮能の指標として左室駆出率(LVEF)が用いられ、それぞれの定義を以下に示します。
- HFrEF:LVEFの低下した心不全(LVEF<40%)
- HFpEF:LVEFの保たれた心不全(LVEF≧50%)
- HFmrEF:LVEFが軽度低下した心不全(40%≦LVEF<50%)
- HFrecEF:LVEFが改善した心不全(LVEF≧40%)
このあたりはカルテで記載されていることがあるので、覚えておくと心不全患者の左室機能を瞬時に理解することができます。
心不全の症状

心不全は以下に分類されます。
- 右心不全
- 左心不全
それぞれの症状について解説していきます。
右心不全
主に体うっ血を主症状とします。
○ 自覚症状
- 右季肋部痛
- 食思不振
- 腹満感
- 心窩部不快感
○ 身体所見
- 肝腫大
- 肝胆道系酵素上昇
- 頚静脈怒張
- 腹水(末期症状)
- 浮腫
- 体重増加
身体所見で観察しやすいものとしては体重増加であり、3日以内に2kg以上の増加では利尿剤の調整が必要です。
心拡大による食道圧迫などにより食思不振に陥る場合があります。
左心不全
主に呼吸関連を主症状とします。
○ 自覚症状
- 呼吸困難
- 息切れ
- 頻呼吸
- 起座呼吸
○ 身体所見
- 水泡音
- 喘鳴
- ピンク色泡沫状痰
- Ⅲ音やⅣ音の聴取
日常生活レベルにおいて呼吸困難感を自覚します。
起座呼吸などでは臥位より長座位の方が楽になるといった起座呼吸も特徴です。
心不全の原因

心不全の原因は以下の2つに大別できます。
- 構造による器質的問題
- 個人因子による問題
それぞれについて解説します。
器質的問題
心臓の構造自体に問題があると心不全を発症します。
主な原因は以下の通りです。
- 心筋梗塞
- 弁膜症
- 心筋炎
- 心筋症
- 先天性心疾患
心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患や、弁膜症による前負荷の増大は心臓に負担がかかり、心臓リモデリングを引き起こします。
個人因子
個人による影響も心不全を発症すると言われています。
- 高血圧
- 肥満
- アルコール
- 喫煙
- 病態理解
再発予防にはしっかりと病態の説明と指導が必要になります。
心不全の治療

心不全治療はいくつかあり、単独ではなく包括的なアプローチが重要となります。
- 薬物療法(内服管理)
- 栄養療法
- 運動療法(有酸素運動)
- 酸素療法(在宅酸素療法:HOT)
心不全の2020年より新薬が注目されているので、これを機に覚えておきましょう。

栄養管理が不十分であると体液が貯留しますし、内服管理を怠ると再発率は高くなります。
運動耐容能は生命予後と関連があると言われているので有酸素運動は非常に重要です。

胸水や肺水腫により酸素化が保たれなくなると、在宅酸素療法も適応になります。
心不全のリハビリテーション

心不全は急性・慢性と分類されるため、以下に示す時期に合わせた介入が重要となります。
- 超急性期
- 亜急性期
- 回復期
- 維持期
それぞれの時期について解説していきます。
超急性期
ICUでは厳格な管理下であることが多く、リスク管理をしながら離床を進めていきます。
廃用や拘縮予防も実施しますが、前・後負荷増加を避けるために負荷量の調整は必要です。
離床については各施設の離床プロトコルに準じ、逸脱例は医師と相談しましょう。
亜急性期
一般病棟に転棟後は、状態を見ながら病前ADLの獲得を目指して介入します。
- 筋力訓練
- 歩行訓練
- ADL訓練
- 患者指導
心不全は再発を繰り返す病気であり、患者指導は重要になります。
場合によっては環境調整やサービスの見直しも必要です。
回復期
状態が安定してきており、機器を使用したレジスタンストレーニングを実施します。
有酸素運動と組み合わせることで効果がより得られやすいといった報告もあります。
維持期
ADL機能を維持するために、筋力訓練、ADL訓練を中心に実施します。
筋力が低下すると、普段のADL動作自体が過負荷になってしまうため、長期臥床だけは避けたいですね。
参考著書
心臓リハビリテーションについても勉強したい方はこちらを。
まとめ
心不全の病態について解説しました。
これからは心不全パンデミックが懸念されているため、心不全患者を担当する機会が増えます。
これを機に心不全について勉強しておきましょう。
心不全関連の記事はこちらから。

心不全関連の記事です。
公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!


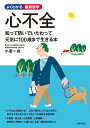




コメント