入院患者に限らず健常人でも貧血症状は起こりますが、貧血の原因には種類があると知っていますか。
原因を知っておくことで担当患者の貧血症状を事前に予測することができます。
今回は貧血の原因やメカニズムについて解説していきます。
この記事を読んでわかること
- 貧血の原因や症状
- 介入前に収集するべき情報
公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!
貧血とは
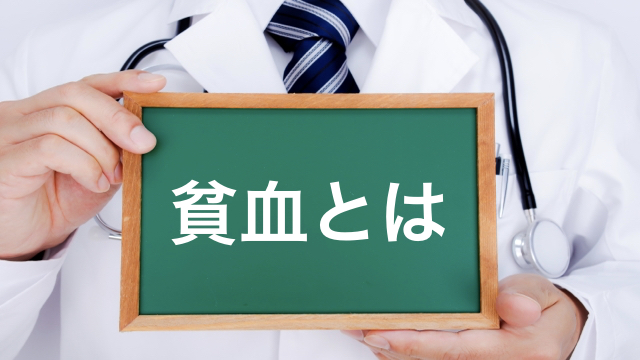
一般的には赤血球に含まれるヘモグロビンの量が少なくなることであり、採血データで確認することができます。
基準値より1~2g/dl低い辺りではそこまで症状を有しませんが、10g/dlを下回ると症状が出現し始めます。
それでは、貧血にはどのような症状があるのでしょうか。
貧血の症状

貧血の症状はさまざまです。
一例ですが臨床で遭遇する症状を下記に示します。
- めまいや立ちくらみ
- 頻脈
- 易疲労性
- 倦怠感
みなさまも臨床でこのような症状を訴える患者を担当したことはありますよね。
それでは、どうしてこのような症状が起きるのでしょうか。
貧血の原因

貧血はヘモグロビンの減少だと解説しましたが、重要なのはどうして減少しているのかについて着目することです。
その原因はさまざまであり、原因によって治療は変わっていきます。
まずは項目でまとめますが、貧血にはこれだけの種類があります。
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
- 巨赤芽球貧血
- 溶血性貧血
- 腎性貧血
- 炎症性貧血
- 心不全による貧血
貧血状態である患者がそのタイプに当てはまるのか考えてみましょう。
鉄欠乏性貧血
ヘモグロビンの産生には鉄が必要になりますが、その鉄が不足してしまうことによって起こる貧血です。
鉄が不足する原因は主に3つに分けられます。
- 出血による鉄の喪失
- 鉄の摂取不足
- 鉄の吸収障害
消化管出血や女性の場合は月経による出血によって鉄が失われます。
また、ダイエットなどの節食では鉄が不足しますし、消化管症状や薬剤により鉄が吸収されにくくなっている場合にも生じます。
再生不良性貧血
血液は第一に骨髄で産生されますが、その骨髄による血球産生機能自体が低下する指定難病に多いです。
ヘモグロビンだけでなく、赤血球や白血球など他の血球の減少することが特徴になります。
先天性や後天性など原因はさまざまであり、以下の病気によって生じます。
- 骨髄異形性症候群(MDS)
- 特発性再生不良性貧血
- 二次性再生不良性貧血
特発性再生不良性貧血は自己免疫異常によって起こるのではないかと言われています。
二次性再生不良性貧血は放射線治療や薬剤による影響が考えられます。
巨赤芽球貧血
赤血球産生に必要な葉酸が不足することで生じる貧血であり、赤血球が大きくなることが名前の由来となります。
胃癌による摘出後患者ではビタミンB12が吸収されにくく、悪性貧血と呼ぶ場合もあります。
葉酸不足はアルコールの多飲や野菜摂取不足などが原因です。
溶血性貧血
溶血性貧血とは赤血球が通常より早く壊され、ヘモグロビンが流出することで起こる貧血です。
溶血性貧血の原因は以下の通りです。
- 自己免疫性溶血性貧血
- 脾臓機能亢進
赤血球の寿命は約120日であり、最終的には脾臓で壊されます。
自己抗体の産生や脾臓機能の亢進により、通常より早く赤血球が壊されてしまいます。
腎性貧血
赤血球の産生には腎臓から産生される造血因子のエリスロポエチンが作られています。
腎臓機能が低下することでエリスロポエチンの産生が減少することで貧血症状を起こします。
腎臓の機能低下では以下の原因が考えられます。
- 糖尿病性腎症
- 慢性腎炎
- 心機能低下による腎血流不足
つまり腎機能を確認することは、貧血症状の進行を予測することにも繋がるということです。
炎症性貧血
炎症症状が貧血を引き起こすといわれて説明できる人は意外と少ないです。
炎症により貧血が起こるのは以下の理由によります。
- サイトカイン産生による骨髄抑制、赤血球寿命の短縮
- アルブミン合成抑制による鉄利用障害
鉄の利用障害では、体内に鉄が不足していなくても生じるため、鉄欠乏性貧血に近い状態になります。
心不全による貧血
心不全が原因で貧血を起こす原因は以下の通りです。
- 体液貯留による血球の希釈(血球濃度低下)
- 腎血流低下による腎性貧血の誘発
心不全患者の貧血症状では因果関係が前後することを忘れないようにしましょう。
例えば、消化管出血などによる貧血由来で心不全を発症している患者もいます。
貧血の治療
まずは貧血の原因となる病気がないかを検査する必要があり、その患者の症状に合った治療を選択することが重要です。
先述した内容をまとめると、(赤)血球産生に必要なものは以下の通りです。
- 鉄
- ビタミンB12
- 葉酸
- エリスロポエチン
これらの要素が不足していないか確認します。
また、鉄の喪失や利用障害の有無なども考慮しましょう。
- 消化管出血
- 偏った食事内容
- 既往歴(胃の摘出後)
- 炎症
原因を特定して薬剤による治療や食事療法などが治療として選択されます。
貧血の予防
鉄は食事から摂取することが大切であり、以下のポイントを守るようにしましょう。
- 3食を規則正しく食べる
- 鉄を多く含む食品の摂取
- 鉄の吸収率を高める(ビタミンC摂取、よく噛む)
- 良質なタンパク質の摂取
他にもサプリで補う方法もおすすめです。
担当する前に必要な情報
担当患者の貧血リスクを予測するうえで最低限確認するべき項目は以下の通りです。
- 採血データ(Hb、Cr、eGFR、CRP、Alb、RBC、Ht)
- 既往歴(消化管出血、胃の摘出後)
- 薬剤(抗凝固薬)
これらで全てではないですが、事前に把握することで貧血症状を察知しやすくなります。
採血データのヘモグロビンの数値だけを確認するのは今日限りで卒業しましょう。
臨床の検査値を活用していきたいと考えている方には、以下の著書がおすすめです。
まとめ
今回は貧血の症状や原因、メカニズムについて解説しました。
ヘモグロビンの減少といってもその原因はさまざまであり、患者背景や病態をしっかりと把握することが大切です。
この記事を読んで貧血に対する考え方が少し変わったのではないでしょうか。
セラピスト関連の記事はこちらからどうぞ

公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!






コメント