みなさんはICU-AWという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
恐らく急性期病院の中でも、ICUや救急に関わる医療従事者でないと関わりが少ないかもしれません。
ICU歴がある患者で、廃用にしては筋力低下が著明な症例っていますよね。
今回は聞き慣れないであろうICU-AW について解説していきます。
公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!
ICU-AWとは

ICU入室患者に生じる神経筋機能低下であり、以下の特徴があります。
- びまん性
- 対称性
- 弛緩性
1980年代あたりから電気生理学的検査が進み、2009年にICU-AWという枠組みをStevensが提唱したことで、診断基準や分類が明確化し、疾患概念が確立しました。
それでは、ICU-AWについてより詳細に解説していきます。
ICU-AWの病態

ICU-AWの病態は複雑で、いまだに解明されていないことも多いです。
筋肉や神経の構造的変化や機能障害についてはさまざまな視点から研究がなされています。
筋繊維は炎症・壊死所見、脂肪組織への置換、繊維化所見が多く観察された。
筋肉タンパク質合成に寄与する遺伝子の発現低下、タンパク質分解酵素の活性亢進が明らかとなった。
Derde:Muscle atrophy and preferential loss of myosin in prolonged critically ill patients.
48時間以上の人工呼吸器管理が見込まれるICU患者では、入院当日と7日目のいずれも筋肉タンパク質の分解が合成を上回っており、タンパク質代謝のアンバランスが筋肉量減少の一因であったとしている。
Purthucheary:Acute skeletal muscle wasting in critical illness.
ICU-AWの病態生理は、大きく3つに分けられています。
CIM:Critical illness myopathy
CIP:Critical illness polyneuropathy
CINM:Critical illness neuromyopathy
ひとつずつ解説していきます。
CIM
敗血症などの重症疾患罹患後に発症する骨格筋障害であり、病態生理は多く提唱されています。
- 骨格筋ユビキチンプロテアソーム経路の活性化
- 骨格筋オートファジー経路の活性化
- 骨格筋新生/再生を抑制
- 骨格筋アポトーシス経路の活性化
- タンパク同化経路の抑制
- ミトコンドリア異常
- ナトリウム/カルシウムチャネル異常
これらを鑑みると、長期臥床由来の単なる廃用ではないということが分かりますね。
CIP
末梢神経軸索障害による運動/感覚神経障害になります。
- 炎症反応に伴う微小循環障害(虚血、変性)
- 神経細胞浮腫によるニューロン機能不全
- 神経筋接合部/神経細胞の興奮低下(Naチャネルの不活性)
炎症によって惹起された末梢神経・神経筋接合部の機能不全がCIPの病態とされています。
CINM
CIMとCIPの合併病態を示し、臨床では多くみられるものになっています。
ICU入室患者では筋力低下だけでなく、神経症状も確認する必要性を理解していただけたでしょうか。
ICU-AWの発生率とリスク因子

これまでICU-AWの研究については施設ごとに対象患者や診断方法、診断時期が異なるため、非常に多くの報告があります。
人工呼吸器患者を対象とした前向き観察研究
○ ICU-AW発症率
111例中66例(59.5%)
○ リスク因子
- 5日間以上の人工呼吸管理
- せん妄
- 3日間以上の高血糖
Diaz BAllve:Weakness acquired in the intensive care unit. Incidence, risk factors and their association with inspiratory weakness.Observational cohort study.
人工呼吸患者を対象とした早期PT・OTの有用性を検討したRCT二次解析
○ ICU-AW発症率
172例中80例(46.5%)
○ リスク因子
- 年齢
- APACHE-Ⅱ score
- 血管作動薬の使用
Wolfe:Impact of Vasoactive Medications on ICU-Acquired Weakness in Mechanically Ventilated Patients.
このようにICU-AWのリスク因子は多岐にわたるので、複数の要素を考慮する必要があります。
報告によって多少は前後しますが、ICU入室患者の約半数に生じる傾向にあるので注意しましょう。
ICU-AWの予後

ICU-AWの発症自体が長期予後に与える影響を検討した報告も多く存在します。
- 自宅退院率の低下
- ICU入室日数の増加
- 横隔膜機能障害の2年生存率は半分以下
- 退院時の自立歩行率低下
ICU-AWを発症しやすい患者集団には予後不良患者が多く、PICS(集中治療後症候群)の原因となり得るので注意してください。
PICS についての記事はこちらから

ICU-AWの予防

現在では有用性が確立されたICU-AWの治療法は存在しないため、予防といった観点が重要視されています。
ICU-AWの予防的介入におけるエビデンスは以下の通りです。
- 血糖コントロール(中等度)
- 早期リハビリテーション(中等度)
- 神経筋電気刺激療法(低い)
*()内はエビデンスの程度
実際には早期リハビリテーション単独による身体機能や筋力、QOLを改善する根拠は乏しいといった報告もあります。
ICU-AWは複数因子が関与しており、栄養療法を組み合わせた介入研究では筋肉量やADL、6分間歩行テストが改善する結果も見受けられました。
PICSの対策にABCDEFGHバンドルが有用とされていることから、ICU-AW予防にも貢献できる可能性があります。
専門・参考著書
より勉強したい方におすすめの著書です。
まとめ
ICU入室患者にみられるICU-AWについて解説しました。
有用な治療は確立されていないので、予防といった観点が重要視されています。
複数の因子が関与しているので包括的ケアが推奨されていますが、早期リハビリテーションの必要性は言うまでもありません。
ICU-AWはPICSの原因とされているので、適切な介入で予防していきましょう。
公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!
他の記事はこちらから
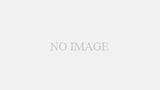







コメント